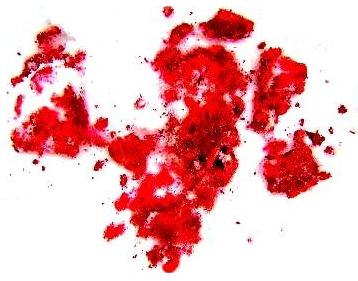
12.
あのスーパーに赴くのは毎回足が重い。なるべくあの母親がいないレジを狙って並ぶのだが、今日並んだ列は、あろう事にあの「こずえ」がレジを打っていた。
周りを見てどうしようか迷ったが、既に後ろにも列が出来ていて、他のレジも同じ状況だったので仕方なく、短くため息を吐き、その場に並んだ。
「いらっしゃいませ」
「どうも」
無言でバーコードを読み取って行く。三つ読み取った所でちらりとこちらを見た。三つ読み取った所で今度は着ているものを見た。財布を見た。鞄を見た。あからさまにむくれた顔をして現金をレジに仕舞い、つり銭を渡した。
普通にしていれば可愛い子だと思うが、このような態度では総司の目には止まるまい。
「どうも」
私は一言言ってその場を立ち去ろうとすると、こずえは一言私に言った。
「もてる男を旦那に持つと、辛いですね」
私は返事をせずに軽く一礼した。
店内は混み合っていた。町の中にまともなスーパーがここにしかないのだから仕方がない。買った物をエコバッグに仕舞おうにも、場所が開かずに立ち尽くしてしまった。
「ここ、どうぞ」
同じぐらいの年齢だろうか、この辺りの人にしては身綺麗にしている女性が、スペースを空けてくれた。
「あ、どうも」
私はそこへ歩いて行き、彼女と入れ替わりで籠を置いた。その時にふんわりと香った匂いに、覚えがあった。
キンモクセイ。キンモクセイの香りだ。
スーパーの自動ドアから出ていく女を目で追った。質の良さそうなキャメルのショートコートに、スキニーデニム、靴はブーティを合わせている。スーパーのロゴが書かれている半透明なビニール袋が浮いて見える。背が高く、スキニーデニムが様になっている。
私は重さなど気にせず、エコバッグに品物を詰め込むと、すぐに駐車場に出た。
キンモクセイの女が乗った軽自動車が発進すると同時に私はキーを回し、エンジンを掛けた。彼女が乗る車の後を追った。
何がしたいのか、自分でもよく分からなかった。彼女を追う事で、何か分かる事があるのかと言えば、家の場所ぐらいだろう。総司との関係なんて、分からない。でも、追わなければ。追って、何かを知りたい衝動に駆られた。
スーパーがある中心街を離れ、自宅の方向へ走る。途中、数回曲がり、道の途中で左ウィンカーが出た。そこには一軒家が立っていた。立派な門が立っている。車はそのまま門の中へ入り、私は後ろから直進してすり抜けた。
門柱には「森崎」という名前が書かれた白い陶器の表札が掲げられていた。
結局私は、総司を疑っている。彼があの日、女と関係を持ったのではないかと。その証拠を探そうとしている。探してどうなる?探して離婚を迫るのか?自分で何をしたいのか、さっぱり分からない。
ただただ、自分の愛する、自分だけを愛してくれていると思っていた総司が、誰かの物になる、誰かに触れられる、それが許せなかった。私の総司。私だけの総司。私だけを見て欲しい。他の誰も見ないで欲しい。
彼からの愛に溺れている。彼への愛に溺れている。この町には、彼を必要とする女が多すぎる。彼からの愛に溺れていいのは、私だけなのだ。
左手の薬指にはめられたプラチナの細いリングを指で撫でた。これがその、証だ。
ファンヒーターをつけ、炬燵に潜りこむ。ふと外を見ると、空から白い物が舞い降りてきたのが見えた。雪だ。この家に越してきて、初めての雪だ。東京で見る雪よりも一粒が大きく、力強い。私はこたつから抜け出して、土間の勝手口から外に出た。
上着も着ていないままなので刺すような冷たい風が身体を襲う。顔に雪がこびり付く。それでも私は空を見上げ、まるで自分にだけ降り注いている様に見えるその白い物体を眺めた。空高くから、猛スピードで私に落下する雪。時々顔のあちこちに落ちてきて痛いのだが、その光景の美しさに、動けない。
隣の家の掃出し窓が開く音がしたが、私はそちらを向かなかった。
「何やってんの、頭おかしいの?」
陽子は嘲笑うように言ったが、気にしなかった。
「雪がそんなに珍しい?東京の人は変わってるね」
そう言ってぴしゃりと窓を閉めた。
私は凍てつく寒さの中、暫く雪の自由落下を下から見上げていた。
「ただいまー。うわー、寒い」
二十三時を回った所で総司が帰宅した。作業着の上にボアがついたジャケットを着て、首をすぼめている。
私はそのジャケットを受け取ると、ボアについた雪を台所のシンクで払い、椅子の背もたれに掛けた。ヒーターをそちらに向け、乾くようにした。
「今日は積もるな。こっちに来て初めてだな」
用意した夕飯をテーブルに並べると、両手を合わせて食べ始めた。
私は彼の対面に座り、食べる様子を見るともなしに見ていた。彼は私の背後にあるテレビのニュースに夢中だった。
「何だ、また中日は負けかぁ。ここんとこ不調だなぁ」
大好きなプロ野球の結果を見ながらぶつくさ言っている。プロ野球ニュースが終わるとリモコンを操作してテレビを消した。
箸をかちかちと鳴らしながら「なぁ、エリカ、そろそろまた子供、作ろうよ」と言った。
私は返事が出来なかった。何故ならキンモクセイが香ってきそうだったからだ。
「子供、欲しくないか?」
不思議そうな顔をして小首をかしげる総司が可愛らしくて、私は下を向いて少し笑ってしまった。
「欲しいと思ってるよ。そうだね、そろそろまた、作ろう」
総司が「子供を作ろう」と言う相手は私だけなのだから。総司の子供は私しか産めないのだから。キンモクセイの香りなんて、私と彼の汗と愛液の匂いで掻き消してやる。
その夜ベッドでセックスをした。
彼は何度も「好きだ」「愛してる」と言葉で言い、それを身体で表現した。私もそれに応えるように、受け入れた。
シャワーを浴びに行った総司を、裸のまま布団に入って待っていると、総司の携帯電話がサイドテーブルでジジジと震えて光った。メールだろうと思いそのままにしておいたが、いつまでも震えが止まらないので着信と分かった。
出るつもりはない。液晶を見るだけ。暗い液晶に光る、黄緑色の文字を。
「森崎昌子携帯」
私は寒さの中に裸で放り出された子供のそれのように、震える手で携帯を掴み、通話ボタンを押した。
『あ、総司?昌子だけど。総司?総司?あれ?』
私は通話終了ボタンを押した。スーパーで聞いたあの声に間違いないだろう。キンモクセイの女。
間髪入れずにもう一度、電話が掛かってきたが、私は布団を頭からかぶり、その振動音が消えるまで堪えた。受け入れたくない現実が、足音を立ててそこまで迫っている。
振動が消えた頃を見計らって布団から顔を出すと、今度は短い振動があって、止まった。
やはり液晶には「森崎昌子携帯」の文字と、メールを示す封筒の絵。さすがにメールまで見ようとは思わなかった。
パジャマを着て、再び布団に入った。
シャワーを浴びて「寒い寒い」と言いながら二階に上がってきた総司は、携帯のライトが点滅しているのを見つけてか、素早く携帯を手にし、内容を確認している。
私は素知らぬ顔で「誰かからの電話?メール?」と訊くと、「この前家から送ってくれた奴からだ」とまるっきり嘘を吐いた。
嘘を吐かずに「森崎という女からだった」と言って欲しかった。その女と総司は何の関係も無い、と否定してくれれば、それで良かった。なのに、何故そこで嘘を吐くのか。
総司に背を向け、目を瞑る。滲み出る涙は重力の法則によって垂れて行き枕へと染み込んでいく。
翌朝、目が覚めた時に見た二階からの景色は圧巻だった。一面真っ白に染まっていた。太陽が昇らないので薄暗く、陰鬱な様子ではあるが、雪に慣れていない私にとっては胸の躍る光景だった。
カーディガンを羽織るとすぐに一階へ降りていき、適当なスニーカーを履いてパジャマのまま外に出た。白い雪はまだ降り続いている。上を見上げると、円錐型に沿って白い雪が顔をめがけて落ちてくるように見える。このまま白い雪に覆われて、真っ白になって、消えてしまえばいいと思った。昨日の夜の電話を思い出したからだ。
「何やってるの?」
起きてきた義母が玄関から不思議そうに顔を出していた。私はさっと赤面した。
「すみません、こういう光景が初めてなので、浮かれてしまって」
雪を踏み鳴らして玄関へ戻ると、「これから暫くは毎日見られるから。安心しなさい」と肩を叩かれた。
買い物から帰る頃には、雪は止んでいた。
車をバックで駐車し、荷物を運び出そうとすると「こんにちは」と声を掛けられた。陽子だった。
「どうも」
私はさも忙しそうに大げさにビニールの音をさせながら荷物を持ち、玄関へ向かおうとした。
ふと、森崎という女の事が気になった。陽子なら、何か知っているかも知れない。
「あの、森崎さんって、どういう方ですか?」
「森崎?」
彼女は目を真ん丸にして、驚いたような、嬉しい様な、待ってましたとばかりの顔をした。
「あれは総司の元カノ。見たの?」
「えぇ、スーパーで」
私は手に持っていたビニール袋を持ち上げてみせた。
「凄く綺麗な方でした」
「見た目だけね。ずっと一緒にいたよ」
彼女の言葉が飲み込めず、「へ?」と素っ頓狂な声を上げてしまった。
「同級会で少なくとも私達が帰るまではずっと、総司の隣にあの子がいた。まるで夫婦みたいに」
私が動揺する様が可笑しいのか、口を押えて笑いを堪えている。
「嘘だと思ったらうちの旦那にでも聞いてみるといいよ。同じ事を言うから」
何処かへ行く途中だったのか、家には戻らず、私の家の前を横切って歩いて行った。
陽子が森崎の事をあまりよく思っていない事は何となく判った。だからこそ、嘘を吐いているように思えない。きっと、同級会の席ではずっと、総司の隣に森崎がいたのだろう。ずっと。宴会が終わっても、ずっと......。
「たまには役に立つじゃん」
そこにいなくなった陽子に対して、口に出して言った。
誰もが総司を欲しがる。誰もが総司を独占したがる。私の、総司。
総司が森崎と何かあったかどうかなんて確証はない。それでも私は、自分以外の他の女が総司に触れる事が許せなかった。隣にいる事が許せなかった。
総司の周りには女が多ぎる。彼の隣には私がいれば良い。それで良いのに。

 
|